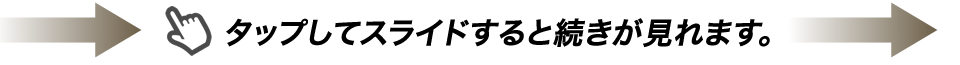2023年10月12日 2024年02月26日
- 骨
- 筋肉
- 免疫
- 肌
「ビタミンDにはどのような効果があるの?」
「ビタミンDは一日にどれくらいとればいいの?」
このような疑問をおもちではありませんか?ビタミンDは、骨を強くしたり免疫機能を正常に働かせたりするために必要な栄養素です。私たちが生活していくうえで欠かせない栄養素だと言えます。
今回は、ビタミンDにはどのような効果や効能があるのか、一日にどれくらいとれば良いのか、ビタミンDを多く含む食品にはどのようなものがあるのかなどを詳しく見ていきましょう。
ビタミンDとは?
ビタミンDは、油に溶けやすい性質をもつ脂溶性のビタミンです。ビタミンDには、ビタミンD2~D7までの6種類があります。このうち、とくに重要なのがビタミンD2(エルゴカルシフェロール)とビタミンD3(コレカルシフェロール)です。
ほかのビタミンDは食品にはほとんど含まれていませんが、そこまで大きな活性もないためあまり重要視はされていません。
ビタミンDを摂取する方法としては、食べ物やサプリメントからとる方法と、日光に当たる方法とがあります。私たち人間は、日光に当たることで自らビタミンDを作り出すことができるのです。日光に含まれている紫外線の一つであるUV-Bを浴びると、皮膚に存在する7-デヒドロコレステロールという物質を材料にビタミンDが生成されます。
十分なビタミンDを生成するために必要なUV-Bを室内で浴びることはできないため、適度な日光浴を行うことが大切です。ただし、過度な日光浴は皮膚がんのリスクを上げてしまうので注意しましょう。
ビタミンDの効果・効能は?
ビタミンDには、次のような効果・効能があることが分かっています。
骨を丈夫にする
ビタミンDは骨を丈夫にするために欠かせない栄養素です。腸管からのカルシウムとリンの吸収を促し、骨の密度を増加させることで骨の強度を高くします。
ビタミンDが不足すると起こるのが「くる病」です。くる病はビタミンDが不足しカルシウムやリンの吸収が悪くなることがおもな原因となって発症します。乳児でくる病が起こることは珍しくありませんので、骨の健康を守るためにもビタミンDはしっかり摂取しておきたいものです。[i]
副腎皮質ステロイドを服用している方の骨の減少を抑制
副腎皮質ステロイドの服用を続けていると、骨粗鬆症のリスクが高まります。ビタミンDを摂取すると、骨の減少を抑制できるため、骨量の減少や骨折の予防をすることが可能です。そのため、高齢者の転倒予防にも効果があると期待されています。
多発性硬化症の予防
多発性硬化症とは、神経を覆う髄鞘が壊れてむき出しになることで脱髄を起こす疾患のことです。視力障害や四肢の麻痺、感覚障害、歩行障害などが起こることで知られています。
現段階でビタミンDが多発性硬化症の予防に効くと断言することはできませんが、効果がある可能性が示唆されています。[ii]
高齢女性の関節リウマチを予防
関節リウマチとは、免疫機能が自分自身を攻撃することで軟骨や骨が破壊され、関節の機能が損なわれる疾患のことです。こちらもビタミンDが効くと断言できるものではありませんが、関節リウマチの発症と関係があるのではと示唆されています。
ある研究では、関節リウマチを発症している方でビタミンDのレベルが有意に低くなっていることが分かりました。関節リウマチとビタミンDの関連性については、今後さらなる研究が行われることが期待されています。[ii]
高齢者の筋力を改善する
ビタミンDが高齢者の筋力を改善する可能性があります。しかし、効果に関しては効くとも効かないとも言い切れないのが現状です。
アスリートを対象とした試験ではありますが、ビタミンD2は筋力に影響を与えないものの、ビタミンD3は筋力にプラスの影響を与えることが分かっています。このことから、もしかしたら高齢者の筋力改善にもビタミンDが役立つかもしれません。[ii]
糖尿病を改善する
ビタミンDがインスリン抵抗性に影響を与えるという研究データもあります。インスリン抵抗性とは、インスリンの効きやすさのことです。抵抗性が高くなるほどインスリンは体内で働きにくくなります。92人の成人を対象にコレカルシフェロール(ビタミンD3)と炭酸カルシウムを16週間にわたり投与したところ、インスリンの分泌が促進されました。[1]
免疫機能を高める
フィンランドでビタミンDと急性気道感染症との関連性について、軍基地労働者を対象に研究が行われました。この研究では、血中のビタミンDの濃度が低い方ほど呼吸器疾患による欠勤が多いことが分かっています。感染症のリスクを抑えることから、免疫機能を高める働きがあることが期待されています。[2]
ビタミンDを含む食材はどんなのがあるの?
ビタミンDを多く含む食材としては、次のものがあります。[iii]
| 食材 | 100gあたりに含まれるビタミンDの量 |
|---|---|
| しらす干し 半乾燥品 | 61.0μg |
| まいわし みりん干し | 53.0μg |
| いくら | 44.0μg |
| あげきくらげ 油いため | 38.0μg |
| にしん | 22.0μg |
| いかなご あめ煮 | 21.0μg |
| 乾燥まいたけ | 20.0μg |
| うなぎ 白焼き | 17.0μg |
| にじます 生 | 11.0μg |
| さんま 生 | 11.0μg |
上記の表を見てもらうと分かる通り、ビタミンDは魚介類やきのこ類、卵類に多く含まれています。身近な食材に多く含まれているため、普段の食事にとりいれやすいでしょう。
ビタミンDは油に溶けやすい性質をもっていることから、油炒めなどのように油を一緒に摂取すると吸収効率が良くなります。
ビタミンDをどのくらいとるのがよいの?
ビタミンDの一日あたりの摂取目安量と耐容上限量は次の通りです。[i]
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |
| 0~5か月 | 5.0μg | 25μg | 5.0μg | 25μg |
| 6~11か月 | 5.0μg | 25μg | 5.0μg | 25μg |
| 1~2歳 | 3.0μg | 20μg | 3.5μg | 20μg |
| 3~5歳 | 3.5μg | 30μg | 4.0μg | 30μg |
| 6~7歳 | 4.5μg | 30μg | 5.0μg | 30μg |
| 8~9歳 | 5.0μg | 40μg | 6.0μg | 40μg |
| 10~11歳 | 6.5μg | 60μg | 8.0μg | 60μg |
| 12~14歳 | 8.0μg | 80μg | 9.5μg | 80μg |
| 15~17歳 | 9.0μg | 90μg | 8.5μg | 90μg |
| 18~29歳 | 8.5μg | 100μg | 8.5μg | 100μg |
| 30~49歳 | 8.5μg | 100μg | 8.5μg | 100μg |
| 50~64歳 | 8.5μg | 100μg | 8.5μg | 100μg |
| 65~74歳 | 8.5μg | 100μg | 8.5μg | 100μg |
| 75歳以上 | 8.5μg | 100μg | 8.5μg | 100μg |
| 妊婦 | 8.5μg | - | ||
| 授乳婦 | 8.5μg | - | ||
.目安量は、一定の栄養状態を維持するために十分な量のことを指します。目安量を摂取していればビタミンDが不足することはほとんどありません。
耐容上限量とは、過剰摂取によって健康被害が出ない最大量のことです。耐容上限量を超えて摂取すると、ビタミンDが過剰になり高カルシウム血症が起こる可能性があります。ビタミンDは脂溶性で体内に蓄積しやすいため、耐容上限量を超えて摂取しないように気をつけましょう。
高カルシウム血症になると、血管壁や腎臓、心筋などにカルシウムが沈着し、腎機能障害や食欲不振などの症状が現れます。
ビタミンDの歴史は?
ビタミンDが発見されたのは、くる病がきっかけです。19世紀のヨーロッパでは、くる病が流行していました。くる病になると、骨が変形したり成長障害が起きたりします。くる病が流行しているなか、イギリスの研究者であるパームが、くる病が発症する地域と日照量に関係があることを明らかにしました。
その後、さらなる研究が行われ、アメリカの研究者がくる病を治す物質を発見します。それがビタミンDです。くる病を治療・予防するためにビタミンDが発見されたと言えます。
ビタミンDの論文一覧
[1]Vitamin D, Autoimmune Disease and Rheumatoid Arthritis
Effects of Vitamin D Supplementation on Muscle Strength in Athletes: A Systematic Review
ビタミンDの参考文献
[ii]同文書院 健康食品・サプリメント[成分]のすべて2017
[iii]食品成分データベース 文部科学省
まとめ
ビタミンDは脂溶性のビタミンとして知られており、おもに骨を丈夫にする働きをもちます。いくつか種類があるビタミンDですが、とくに活性が高いのがビタミンD2とビタミンD3です。魚介類やきのこ類、卵類に多く含まれているので、これらの食材を積極的にとるようにしましょう。
ビタミンDが不足すると腸管からのカルシウムの吸収が低下するため、低カルシウム血症になることがあります。魚介類やきのこ類を普段からあまり食べない方、日光に当たる機会が少ない方はサプリメントを活用するとよいでしょう。
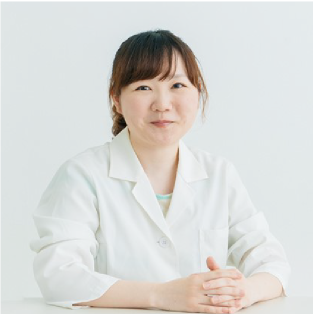
- 記事の監修岡本妃香里
- 2014年に薬学部薬学科を卒業し、薬剤師の資格を取得。大手ドラッグストアに就職し、調剤やOTC販売を経験する。2018年に退職し、現在は医療ライターとして医薬品や化粧品、健康食品など健康と美に関する正しい情報を発信中。
Posted by hecola.