2023年10月24日 2024年02月26日
- 免疫
- お腹
- 体力
亜鉛は、味覚を保ったり細胞の修復をしたりする効果があると言われています。ドラッグストアや薬局でサプリメントが販売されているため、ご存知の方が多い成分でしょう。
亜鉛は男性向けの成分と思われることがありますが、決してそのようなことはありません。性別問わず、亜鉛はしっかり摂りたい成分の一つです。
今回は、亜鉛にはどのような効果があるのかについて詳しく解説します。一日の摂取目安量や過剰摂取したときの影響についても紹介しているので参考にしてみてください。
亜鉛とは?[i]
亜鉛とは、体に必要不可欠なミネラルの一種です。必要な量は極わずかですが、体内で作ることができず、健康を維持するために欠かせないことから必須微量元素と呼ばれています。
体内に存在する亜鉛の量は約2~3gです。その多くは皮膚や肝臓、膵臓や前立腺などの臓器に存在しています。
日常生活で亜鉛が不足することはあまりありませんが、発展途上国では亜鉛不足に陥っている方がまだ少なくありません。亜鉛が不足すると、発育不全や下痢、脱毛症などを引き起こす恐れがあります。
200種類以上もの酵素の反応や活性化に関与しており、私たちが健康に過ごすためには必須の成分です。最近の研究では、免疫反応に関わっていることも分かってきました。
亜鉛が免疫細胞の働きを活性化する働きがあるのです。亜鉛は一般の方が摂取目安量を守って使用する限りでは安全性が高いと考えられています。ただし、傷のついた肌に亜鉛を塗布すると鋭い痛みやかゆみを感じることがあるので注意してください。
また、糖尿病の方が亜鉛を多量に摂取すると血糖値が下がってしまう恐れがあります。糖尿病の治療薬を使用している場合は必要以上に血糖値が下がることがあるため、多量摂取はしないようにしましょう。
妊娠中や授乳中の方に関しては、摂取目安量を守って使用する範囲なら安全性に問題はないと考えられています。ただし、授乳中の方が多量摂取するのは安全ではないとする声もあるため、摂取目安量は必ず守って使用してください。
亜鉛の効果・効能は?
亜鉛の効果・効能としては、主に次のようなものが知られています。
下痢の改善
発展途上国では、下痢が致命傷となって死亡する小児がしばしば見られます。このような例で亜鉛の摂取が有効です。亜鉛を使用すると下痢の症状を緩和できることが分かっています。[ii]
免疫機能を高める
亜鉛は免疫機能が正常に働くために必要な成分です。亜鉛が欠乏したり逆に過剰になったりすると、免疫細胞に障害が起きて感染症にかかりやすくなることが分かっています。とくに亜鉛が欠乏した場合はT細胞など獲得免疫に関わっている細胞の働きが低下してしまうことが明らかです。[2]
味覚障害の改善
亜鉛不足は味覚障害を引き起こす原因です。味覚を感じる味蕾という器官の再生には、亜鉛が必要になります。そのため、亜鉛が不足すると味蕾の働きが落ちて味覚障害が起きてしまうのです。
亜鉛は体内で合成したり蓄えたりすることができないため定期的に摂取を続ける必要があります。ただし、味覚障害が起こる原因は亜鉛不足だけが原因ではありません。ほかに原因があるケースもあるため、症状が出たときは念のため医療機関の受診をおすすめします。[3]
風邪の治療を早める
風邪にかかった際にドロップタイプの亜鉛を使用すると、治癒が早まることが分かっています。亜鉛を摂取するタイミングとしては、風邪の発症から24時間以内が効果的です。[i]
インドで行われた研究によると、1日あたり75mg以上の亜鉛を使用することで風邪の期間が短縮されることが報告されています。
血糖値を低下させる
糖尿病の患者に亜鉛を摂取させると、血糖値が低下することが分かっています。亜鉛には、インスリンの合成を促進したり、膵β細胞からのインスリン放出を促したりする働きがあるのです。治療を受けているにもかかわらず血糖値のコントロールが悪い糖尿病の患者では、亜鉛が不足しているとのデータもあります。そのため、亜鉛が糖尿病の治療に役立つ可能性があると言えるでしょう。[i]
ただし、糖尿病治療薬と併用すると過度に血糖値が下がる恐れもあるため、必ず医師や薬剤師に相談してから亜鉛を摂取するようにしてください。
精子の活性化
亜鉛は精子を活性化するのに必要な成分だと言われています。亜鉛が不足すると精子濃度が低下したり運動率が悪化したりすると言われているため、男性の生殖機能を保つために必要な成分だと言えるでしょう。ただし、亜鉛がどの程度の有効性を示すのかについてはまだ明確には分かっていません。[4]
亜鉛を含む食材はどんなのがあるの?
亜鉛を多く含む食材には、次のようなものがあります。[iii]
| 食品名 | 100gあたりに含まれる亜鉛の量 |
|---|---|
| 牡蠣 | 25.0mg |
| 小麦胚芽 | 16.0mg |
| スモークレバー(豚) | 8.7mg |
| かぼちゃ | 7.7mg |
| 牛のもも肉 | 7.5mg |
| パルメザンチーズ | 7.3mg |
| ピュアココア | 7.0mg |
| まいたけ(乾燥) | 6.9mg |
| 豚の肝臓 | 6.9mg |
| 抹茶 | 6.3mg |
もっとも亜鉛を多く含む食品は、牡蠣です。身近な食べ物だと牛や豚などがあります。食品から摂取するのが難しい場合は、サプリメントを使用するのもおすすめです。簡単に一日に必要な量を摂取できます。ただし、摂取目安量を超えて使用すると過剰摂取につながる恐れもあるため、必ず量を守って服用してください。
亜鉛をどのくらいとるのがよいの?
亜鉛の推定平均必要量や目安量などは次のとおりです。[iv]
| 年齢 | 男性 | 女性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 | |
| 0~5か月 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 6~11か月 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 1~2歳 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | - |
| 3~5歳 | 3 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 6~7歳 | 4 | 5 | - | - | 3 | 4 | - | - |
| 8~9歳 | 5 | 6 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 10~11歳 | 6 | 7 | - | - | 5 | 6 | - | - |
| 12~14歳 | 9 | 10 | - | - | 7 | 8 | - | - |
| 15~17歳 | 10 | 12 | - | - | 7 | 8 | - | - |
| 18~29歳 | 9 | 11 | - | 40 | 7 | 8 | - | 35 |
| 30~49歳 | 9 | 11 | - | 45 | 7 | 8 | - | 35 |
| 50~64歳 | 9 | 11 | - | 45 | 7 | 8 | - | 35 |
| 65~74歳 | 9 | 11 | - | 40 | 7 | 8 | - | 35 |
| 75歳以上 | 9 | 11 | - | 40 | 6 | 8 | - | 30 |
| 妊婦(付加量) | +1 | +2 | - | - | ||||
| 授乳婦(付加量) | +3 | +4 | - | - | ||||
亜鉛を過剰摂取すると、銅の吸収障害が起きることにより銅欠乏症が起こる恐れがあります。銅欠乏症になると貧血や骨異常、毛髪異常、白血球減少、神経系の異常などが起こることがあるので注意しましょう。
また、頭痛や倦怠感、吐き気や腹痛、下痢、食欲不振などが起こることも報告されています。
亜鉛の歴史は?
亜鉛は紀元前4,000年から銅の合金である黄銅として用いられてきました。生体内では100種類を超える酵素の活性に関与しています。免疫機能や味覚、小児の成長などに関わっている成分です。
1961年にイランで成長遅延が見られる子どもを研究したことがきっかけで亜鉛の欠乏症が発見されました。亜鉛不足の子どもでは貧血や性機能の低下が見られていましたが、亜鉛を補充することで症状が改善しています。
成人の亜鉛欠乏症は、1975年に発見されました。高カロリー輸液のみで栄養補給が行われている患者で、欠乏症の症状が見られたのです。
亜鉛の論文一覧
[2]The role of zinc in the treatment of taste disorders
[4]Zinc is an intracellular signal during sperm activation in Caenorhabditis elegans
亜鉛の参考文献
[i]健康食品・サプリメント[成分]のすべて2017
[ii]厚生労働省eJIM | 亜鉛 | サプリメント・ビタミン・ミネラル | 一般の方へ | 「統合医療」情報発信サイト
[iii]食品成分データベース 文部科学省
まとめ
亜鉛は私たちの体を動かすのに欠かせない成分です。皮膚や肝臓、前立腺などに多く存在しています。下痢の改善をしたり免疫機能を高めたりする効果があることが特徴です。
亜鉛を多く含む食品としては、牡蠣や豚、牛などが知られています。日常の食生活でも摂取できますが、無理なく摂り続けたい方はサプリメントを活用するとよいでしょう。
摂りすぎると銅欠乏症になったり頭痛や倦怠感が出たりする原因になるため、必ず摂取目安量を守って使用してください。
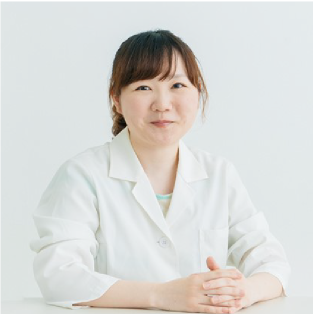
- 記事の監修岡本妃香里
- 2014年に薬学部薬学科を卒業し、薬剤師の資格を取得。大手ドラッグストアに就職し、調剤やOTC販売を経験する。2018年に退職し、現在は医療ライターとして医薬品や化粧品、健康食品など健康と美に関する正しい情報を発信中。
Posted by hecola.



